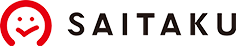小規模事業者持続化補助金について、2022年度補正予算案で判明した小規模事業者持続化補助金についてお伝えします。
目次
小規模事業者持続化補助金の概要
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が働き方改革などの制度変更等に対応するため経営計画を作成したり、それらに基づいて売上アップのための販路開拓や業務の効率化を図るための取組をしたりする時にかかる経費の一部を補助する補助金の事です。
補助金の対象者
小規模事業者持続化補助金の対象者は、小規模事業者以下の要件を満たす特定非営利活動法人です。
- 商業・サービス業:5人以下
- 宿泊業・娯楽業:20人以下
- 製造業その他:20人以下
※従業員数に社長やアルバイトの人数はカウントされません。
※申請時点で開業していない創業予定者の他、一般社団法人や公益社団法人、医師・歯科医師・助産師、医療法人、学校法人、宗教法人などは対象となりません。
対象経費
小規模事業者持続化補助金の対象経費には、次のものが挙げられます。
- 機械装置等費:新商品を陳列するための棚の購入など
- 広報費:新たな販促用チラシの作成や看板作成、設置費用など
- ウェブサイト関連費:ウェブサイトや ECサイト等の構築など(補助対象経費の4分の1が上限)
- 展示会等出展費:国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加など
- 旅費
- 開発費:新商品の開発など
- 資料購入費:新商品の開発にあたって必要な図書の購入など
- 雑役務費:新たな販促用チラシのポスティングなど
- 借料:国内外での商品PRイベント会場の借り上げなど
- 専門家謝金:ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導や助言など
- 専門家旅費
- 委託費:新商品開発に伴う成分分析の依頼など
- 外注費:小売店の店舗改装にともなう陳列レイアウト改良や飲食店の店舗改修など(ただし、不動産の購入や取得に該当するものは不可)
- 設備処分費(補助対象経費総額の2分の1が上限)
これらのうち次の項目すべての要件を満たすもののみが補助対象となっています。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払が完了した経費
- 証拠資料などによって支払金額が確認できる経費
2022年度補正予算分の小規模事業者持続化補助金の各補助金額と補助率
- 通常枠:50万円、補助率は3分の
- 通常枠:50万円、補助率は3分の2
- 卒業枠:200万円
- 賃金引き上げ枠:200万円、補助率は3分の2(赤字事業者は3/4)
- 後継者支援枠:200万円、補助率は3分の2
- 創業枠:200万円、補助率は3分の2
- インボイス枠(インボイス発行事業者への転換):100万円、補助率は3分の2
2022年度補正予算、小規模事業者持続化補助金の概要
「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者等が経営計画を策定して、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等の取組を支援するために実施されます。
○補助額:上限 50~200万円
○補助率:2/3(賃金引上げ枠で、赤字事業者は3/4)
令和3年度補正予算(2022年度実施)では、以下の特別枠が設定されます。
■賃金引上げ枠
■卒業枠
■後継者支援枠
■創業枠
■インボイス枠
2022年度(令和4年度)小規模事業者持続化補助金の特別枠
2022年度(令和4年度)では、通常枠の他、以下の特別枠が設定されています。
通常枠
通常枠は、小規模事業者持続化補助金のもっとも基本となる枠です。
「小規模事業者持続化補助金」とはこの通常枠を指すことが多い。
多くの事業者が申請している。
賃金引上げ枠
補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上(すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上)とした事業者に対して、補助上限額を200万円へと引き上げる特別枠です。
また、本枠を申請する事業者のうち業績が赤字の事業者は、補助率を3/4へ引き上げると共に政策政策加点による優先採択が実施されます。
※補助事業の終了時点において要件を満たしていない場合は交付決定後であっても補助金の交付はなされません。
卒業枠
卒業枠とは、補助事業の終了時点において常時使用する従業員の数を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて事業規模の拡大を目指している事業者に対して、補助上限額を200万円へと引き上げる特別枠です。
「卒業枠」を検討されている方は、補助事業修了時点において、下記従業員数よりも多い従業員を常時使用している必要があります。
- 商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く):5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
- 製造業・その他:20人以上下
後継者支援枠
後継者支援枠とは、将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補とし申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者を対象に、制作支援をするため、補助上限額を200万円へと引き上げる特別枠です。
アトツギ甲子園とは、全国各地の中小企業の後継者・後継者候補(アトツギ)が家業を活かした新規事業アイデアを競うピッチイベントであり、中小企業庁が主催しています。西日本・中日本・東日本の3ブロックで地方予選大会を設けられ、地方予選大会を勝ち抜いた後継者が決勝大会(ファイナル)に進むことができます。
創業枠
創業枠とは、販路開拓の新しい取組を応援する、創業3年以内の事業者を対象に、補助上限額を200万円へと引き上げる特別枠です。
※過去3年の間に開業し、かつ産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3年の間に受けた事業者のことを言います。
インボイス枠
インボイス枠とは、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者または免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求)発行事業者に登録した事業者に対して、補助上限額を100万円へ引き上げる特別枠です。
※ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は補助金の交付がされません。
インボイス(適格請求書)とは売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
令和5年(2023年)10月1日からのインボイス制度が開始されると、消費税納税義務がある課税事業者は商取引において、税率・税額を明記した文書を発行しなくてはなりません。また、取引相手から求められたときは当該文書を交付する義務も負います。
※この文書は適格請求書発行事業者しか発行できません。
小規模事業者持続化補助金、申請から受給までの流れ
小規模事業者持続化補助金は申請して採択がされても他の補助金と同様にすぐに補助金が振り込まれるわけではありません。
2022年度における申請から受給までの全体の流れは次の通りです。
①申請
⇓
②採択・酢採択の通知が届く
⇓
③補助事業を開始する
⇓
④補助事業実施の報告書を提出
⇓
⑤補助金額の確定検査
⇓
⑥補助金を請求する
⇓
⑦補助金の入金
⇓
⑧事業効果報告
申請する
経営計画書や補助事業計画書を作成し、地域の商工会議所で確認を受けます。
無事に確認が終わり支援機関確認書の作成の交付が受けられたら、補助金事務局である日本商工会議所へ申請書類一式を郵送またはJグランツから電子で申請します。
なお、社外の代理人のみで地域の商工会議所への相談や支援機関確認書の交付依頼などを行うことは好ましくないとされています。
採択・不採択が決定される
公募締切日からおおむね2ヶ月後くらいに日本商工会議所から採択または不採択の通知がされます。小規模事業者持続化補助金のうち一般型の採択率は回を追うごとに低下の傾向があり、回によっては狭き門となっています。
申請をした取り組みを実施する
無事に採択されたからといって、すぐに補助金が振り込まれるわけではありません。先に、申請をした内容に沿って補助対象事業を実施(補助対象とする経費の支出)をする必要があります。
経費の支払いに直接補助金を充てることはできません。手持ちの資金が不足する場合には、金融機関などから一時的に資金を借り入れる「つなぎ融資」を受けたり資金の準備が必要となります。
取り組み実施の報告書を提出する
補助対象事業の実施したら、所定の期間内に実施報告書を提出します。
実施報告の際には、経費の領収書など支出を証明する書類などの資料を添付しなければなりません。
そのため、あらかじめ必要な資料を確認し、紛失したり相手方から受領しそびれてしまったりすることのないよう十分注意してください。
補助金が交付される
日本商工会議所が提出した実施報告を確認し問題がないと判断されれば、ようやく補助金を受領することができます。
小規模事業者持続化補助金、申請スケジュール
2022年度における小規模事業者持続化補助金の公募スケジュールは次のとおりです。
- 第8回締切:2022年6月3日(金)(事業支援計画書発行の受付締切:原則2022年5月27日(金))
- 第9回:2022年9月中旬(事業支援計画書発行の受付締切:原則2022年9月上旬)
- 第10回:2022年12月上旬 (事業支援計画書発行の受付締切:原則2022年12月上旬)
- 第11回:2023年2」月下旬(事業支援計画書発行の受付締切:原則2023年2月中旬)
申請を希望する公募回の締切に合わせて、計画的に準備を進めるようにしましょう。
まとめ
小規模事業者持続化補助金は対象となる経費の幅が広いため、小規模事業者にとって活用しやすい補助金の一つです。経費の一部が補填される可能性がありますので申請してみてはいかがでしょうか?
補助金申請が初めてだったり、補助金の申請に時間を割くことが難しかったりする場合は、多くの資料が必要のため手間もかかり自社のみで行うことは容易な事ではありません。そのため公募開始前から専門家へ相談しておくことをおすすめします。公募開始前からスケジュールを立てて準備を進めることで、公募開始後スムーズに申請することが可能になります。
SATAKUでは、補助金の申請サポートに力を入れており補助金・助成金を検討される際にはお気軽にご相談くださいませ。